
胡蝶蘭についてはコチラもお読みください。
突然の訃報に接し、深い悲しみのなか、お悔やみの気持ちをどのように伝えればよいか戸惑う方は少なくありません。
特に、弔電を手配する際には、お悔やみの電報は縦書きか横書きかという基本的な書式から、宛名や差出人の書き方、そしてどのような言葉を選べば失礼にあたらないかなど、さまざまなマナーやルールに悩むことでしょう。
急なことであっても、故人を偲び、ご遺族に寄り添う気持ちをきちんと形にして届けたいものです。
この記事では、お悔やみの電報を送る際に多くの方が疑問に思う、縦書きと横書きの選択基準をはじめ、弔電に関するあらゆるマナーを網羅的に解説します。
NTTなどの電報サービスを利用する際の台紙の選び方、故人との関係性に応じた敬称の正しい使い方、会社名義や連名で送る場合の具体的な記載方法、そして注意すべき句読点のルールや避けるべき忌み言葉についても詳しく触れていきます。
さらには、心のこもったメッセージを伝えるための文例や、喪主をはじめとするご遺族への配慮についても丁寧に説明します。
この記事を最後までお読みいただくことで、弔電に関する不安や疑問が解消され、自信を持って心からのお悔やみの言葉を届けられるようになるでしょう。
また、弔電だけでなく、供花や香典といった他の弔意の示し方についても触れ、故人への最後の贈り物としてふさわしい選択ができるようお手伝いします。
- ➤お悔やみの電報で縦書きと横書きのどちらを選ぶべきか
- ➤弔電の台紙選びのポイントとレイアウトの関係性
- ➤NTTなどの電報サービスで利用できる文例や書体
- ➤故人や喪主に対する正しい敬称の使い方
- ➤会社名義や連名で弔電を送る際の注意点
- ➤句読点や忌み言葉といった弔電特有のルール
- ➤弔電と合わせて検討したい供花などの弔意の示し方
お悔やみの電報は縦書きか横書きかの基本的なマナー
- ➤一般的には縦書きがより丁寧な印象
- ➤弔電の台紙の選び方とレイアウトの関係
- ➤信頼できるNTTの電報サービスと書体
- ➤すぐに使える心のこもった文例の探し方
- ➤敬称の使い分けで故人への敬意を示す
一般的には縦書きがより丁寧な印象

お悔やみの電報を送る際、多くの方が最初に悩むのが、お悔やみの電報は縦書きか横書きか、という書式の選択ではないでしょうか。
結論から申し上げますと、弔電においては、一般的に縦書きがより丁寧で正式な形式とされています。
これは、日本の伝統的な筆記スタイルが縦書きであることに由来します。
特に、目上の方やビジネス関係者、ご年配の方へ送る場合、あるいは格式を重んじる場面では、縦書きを選ぶのが最も無難であり、敬意を示す作法として受け入れられやすいでしょう。
縦書きは、厳粛な雰囲気を醸し出し、故人への深い哀悼の意とご遺族への心遣いをより強く表現する効果があります。
手紙文化が根付いている日本では、改まった内容や儀礼的な文書は縦書きで記すという慣習が今なお残っており、弔電もその一つと位置づけられています。
一方で、横書きがマナー違反というわけでは決してありません。
近年では、特に親しい友人や同僚など、気心の知れた間柄の方へ送る場合に横書きが選ばれることも増えています。
横書きは、より親しみやすく、現代的な印象を与えるため、メッセージの内容や故人との関係性によっては適している場合もあります。
例えば、メッセージにアルファベットや数字が多く含まれる場合、横書きの方が見やすく、レイアウトもすっきりとまとまります。
また、デザイン性の高い洋風の台紙を選ぶ際には、横書きの方が全体の雰囲気に調和することもあります。
どちらを選ぶか迷った場合は、故人との関係性、ご遺族の状況、そしてご自身の立場を総合的に考慮して判断するのがよいでしょう。
もし判断に迷うのであれば、より丁寧な印象を与える縦書きを選んでおけば、失礼にあたることはまずありません。
重要なのは、書式そのものよりも、故人を悼み、ご遺族を慰める気持ちです。
その気持ちを最も誠実に伝えられるとご自身が感じる形式を選ぶことが、何よりも大切と言えるでしょう。
最終的な判断基準として、以下の点を参考にしてみてください。
- 目上の方や恩師、取引先など:縦書きを推奨します。
- 親しい友人や同僚:縦書きが無難ですが、横書きでも問題ありません。
- デザイン性の高い台紙:台紙のデザインに合わせて縦書きか横書きかを選びます。
- メッセージの内容:アルファベットや数字が多い場合は横書きが見やすいことがあります。
これらの点を踏まえ、お悔やみの気持ちが最も伝わる形式を選んでください。
弔電の台紙の選び方とレイアウトの関係
お悔やみの電報は、メッセージの内容だけでなく、それを受け取るご遺族の目に最初に触れる台紙も非常に重要です。
台紙は弔意を形として示すものであり、その選び方一つで、お悔やみの気持ちの伝わり方が変わってきます。
台紙を選ぶ際には、故人の人柄やご遺族の悲しみに配慮し、落ち着いたデザインのものを選ぶのが基本的なマナーです。
弔電用の台紙には、さまざまな種類があります。
例えば、伝統的な菊や蓮の花をあしらった和風のデザイン、刺繍や押し花が施された高級感のあるもの、シックでモダンな洋風のデザインなど多岐にわたります。
台紙の選び方のポイントは、故人のイメージや宗教に合わせて選ぶことです。
仏式であれば蓮の花、神式やキリスト教式であればユリの花などが描かれた台紙がよく用いられます。
もし故人の宗教が不明な場合は、特定の宗教色がない、落ち着いたデザインの台紙を選ぶのが無難です。
例えば、淡い紫やグレーを基調としたシンプルなデザインや、山や川などの自然をモチーフにしたものが良いでしょう。
そして、この台紙のデザインは、メッセージのレイアウト、つまり縦書きか横書きかという選択とも密接に関係してきます。
一般的に、和風のデザインや伝統的な柄の台紙には、縦書きのレイアウトがよく調和します。
筆文字のような書体と組み合わせることで、より一層厳かで心のこもった印象を与えることができます。
一方で、スタイリッシュな洋風のデザインや、横長のデザインの台紙の場合は、横書きのレイアウトの方がすっきりとまとまり、全体のバランスが良くなります。
電報サービスによっては、台紙のデザインごとに推奨されるレイアウトが決まっている場合もありますので、申し込みの際に確認するとよいでしょう。
台紙の価格帯もさまざまですが、必ずしも高価なものが良いというわけではありません。
故人との関係性を考慮し、ご自身の予算の範囲で、最もお悔やみの気持ちが伝わると思われるものを選びましょう。
例えば、親しい友人であれば、故人が好きだった花の押し花があしらわれた台紙を選ぶなど、少しパーソナルな要素を加えるのも良いかもしれません。
会社として送る場合は、華美になりすぎず、それでいて品格のある、落ち着いたデザインの刺繍台紙などが適しています。
最終的に、台紙とレイアウトの組み合わせは、ご遺族が受け取った際に、送り主の温かい心遣いが感じられるようなものを選ぶことが最も重要です。
信頼できるNTTの電報サービスと書体

弔電を送る際、どの電報サービスを利用するかという点も重要です。
日本国内で最も広く知られ、信頼性が高いサービスの一つがNTTの電報サービスです。
NTTは全国に広がる通信網を活かし、迅速かつ確実に電報を届けてくれるため、急な訃報に際しても安心して依頼することができます。
特に、通夜や告別式の日時が迫っている場合には、その信頼性は大きな安心材料となるでしょう。
NTTの電報サービス(D-MAIL)では、弔電専用の台紙が豊富に用意されています。
前述したような伝統的な和風のものから、モダンな洋風のもの、さらには線香やプリザーブドフラワーがセットになったものまで、幅広い選択肢から選ぶことができます。
これにより、故人の人柄やご遺族への気持ちに合わせた、最適な弔電を手配することが可能です。
ウェブサイトから24時間いつでも申し込むことができ、文例集も充実しているため、初めて弔電を送る方でもスムーズに手配を進められる点も大きなメリットです。
さらに、メッセージを作成する上で見落としがちですが重要な要素が「書体(フォント)」の選択です。
NTTの電報サービスでは、メッセージを印字する際の書体を選ぶことができます。
弔電でよく用いられる書体には、「楷書体」や「明朝体」があります。
- 楷書体:一画一画を続けずに書く、丁寧で読みやすい書体です。手書きのような温かみがあり、弔電の書体として最も一般的で、どのような場面でも失礼にあたりません。真心を込めてお悔やみを伝えたい場合に最適です。
- 明朝体:活字として馴染み深く、こちらもフォーマルな場面で広く使われます。知的で落ち着いた印象を与え、特にビジネス関係の弔電などで選ばれることが多いです。
書体は、メッセージ全体の印象を大きく左右します。
例えば、同じ文章でも、温かみのある楷書体で印字されているのと、シャープなゴシック体で印字されているのとでは、受け取る側の印象は大きく異なります。
弔電においては、奇抜な書体や装飾的な書体は避け、故人を偲ぶ気持ちが伝わる、落ち着いていて読みやすい書体を選ぶことが大切です。
お悔やみの電報は縦書きか横書きかというレイアウトの選択と合わせて、この書体の選択にも配慮することで、より心のこもった弔電を送ることができるでしょう。
NTTの申し込み画面では、レイアウトや書体を選んだ際のプレビュー機能があるため、実際にどのように印字されるかを確認しながら、最適な組み合わせを選ぶことをお勧めします。
すぐに使える心のこもった文例の探し方
いざ弔電を送ろうとしても、どのような言葉を選べばよいのか、筆が進まないという方は多いものです。
悲しみの場に送る言葉だからこそ、失礼があってはならない、ご遺族の心を傷つけてはいけないという気持ちから、慎重になるのは当然のことです。
そのような時に大変役立つのが、電報サービス会社などが提供している「文例集」です。
NTTをはじめとする主要な電報サービスのウェブサイトには、さまざまな状況に応じた弔電の文例が数多く掲載されています。
これらの文例は、弔電のマナーに則って作成されているため、そのまま使うだけでも失礼にあたることはありません。
文例を探す際には、まず「故人との関係性」を基準に探すのが効率的です。
文例集は通常、以下のように分類されています。
- ご親族(祖父母、父母、兄弟姉妹、配偶者の親族など)向け
- ご友人・知人向け
- 会社関係(上司、同僚、部下、取引先)向け
- 恩師・先生向け
- キリスト教など、特定の宗教の方向け
例えば、会社の同僚のお父様が亡くなられた場合は、「会社関係」の中の「社員の家族」向けの文例を探します。
これにより、立場にふさわしい言葉遣いや表現を簡単に見つけることができます。
しかし、文例をそのまま使うことに抵抗がある、もっと自分の言葉で気持ちを伝えたい、と考える方もいらっしゃるでしょう。
その場合は、文例をベースに、ご自身の言葉でアレンジを加えるのがおすすめです。
すべてを自分で考えるのは難しくても、一部分を書き換えるだけで、オリジナリティのある心のこもったメッセージになります。
アレンジを加える際のポイントは、故人との思い出を具体的なエピソードとして一文加えることです。
例えば、「ご生前の笑顔ばかりが思い出され、胸がいっぱいになります」という文例に、「〇〇の席でご一緒させていただいた際の、優しい笑顔が忘れられません」のように具体的な場面を付け加えるだけで、ぐっと気持ちが伝わる文章になります。
ただし、長々と書き連ねるのは避け、簡潔にまとめるのがマナーです。
また、文例を探す際には、忌み言葉や敬称の使い方など、弔電の基本的なルールが守られているかを確認することも大切です。
信頼できる電報会社の文例集であればその心配はほとんどありませんが、インターネット上の不確かな情報を参考にする際は注意が必要です。
心のこもったメッセージを送るために、まずは信頼できる文例集をいくつか読み比べてみて、ご自身の気持ちに最も近いものを選び、そこに故人を偲ぶあなた自身の言葉を少しだけ添えてみてはいかがでしょうか。
敬称の使い分けで故人への敬意を示す
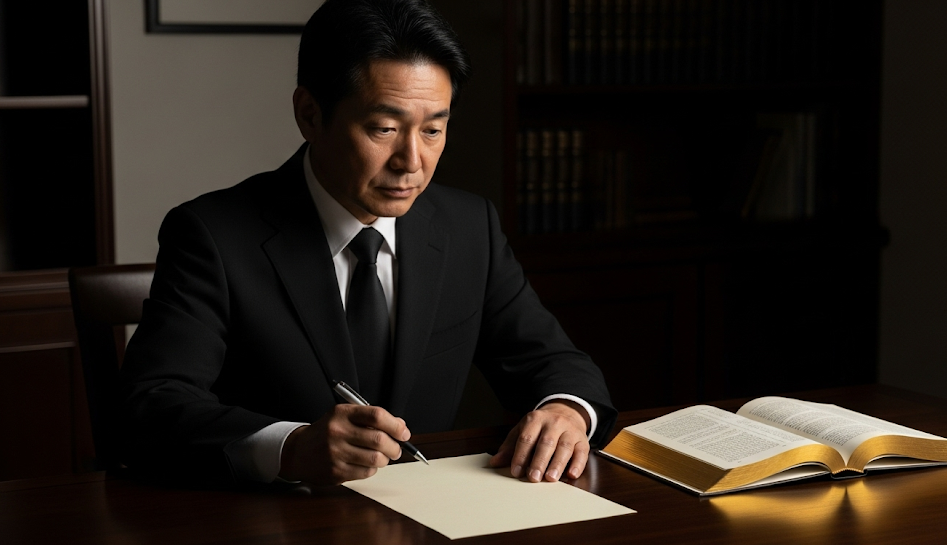
弔電を作成する上で、最も間違いやすく、かつ非常に重要なのが「敬称」の使い方です。
敬称とは、故人やご遺族に対して敬意を示すための言葉であり、これを間違えると大変失礼にあたってしまいます。
弔電の宛名は通常、喪主の方になりますが、本文中で故人に言及する際には、喪主から見た故人との続柄に応じた敬称を用います。
例えば、喪主である〇〇様宛ての電報で、亡くなったのが〇〇様のお父様であれば、「お父様」と直接的に書くのではなく、「ご尊父様(ごそんぷさま)」や「お父上様(おちちうえさま)」といった敬称を使います。
この敬称の使い分けは複雑で覚えにくい部分でもありますが、故人への深い敬意を表すために不可欠なマナーです。
以下に、主な続柄に対する敬称をまとめましたので、弔電を送る際の参考にしてください。
主な敬称の一覧表
| 喪主から見た続柄 | 敬称 | 読み方 |
|---|---|---|
| 父 | ご尊父様、お父上様 | ごそんぷさま、おちちうえさま |
| 母 | ご母堂様、お母上様 | ごぼどうさま、おかあうえさま |
| 夫 | ご主人様、ご夫君様 | ごしゅじんさま、ごふくんさま |
| 妻 | ご令室様、ご令閨様 | ごれいしつさま、ごれいけいさま |
| 祖父 | ご祖父様、御祖父様 | ごそふさま、おじいさま |
| 祖母 | ご祖母様、御祖母様 | ごそぼさま、おばあさま |
| 息子 | ご子息様、ご令息様 | ごしそくさま、ごれいそくさま |
| 娘 | ご息女様、ご令嬢様 | ごそくじょさま、ごれいじょうさま |
| 兄 | ご令兄様 | ごれいけいさま |
| 弟 | ご令弟様 | ごれいていさま |
| 姉 | ご令姉様 | ごれいしさま |
| 妹 | ご令妹様 | ごれいまいさま |
ポイントは、差出人である自分から見た関係ではなく、電報を受け取る喪主から見た関係で敬称を選ぶことです。
例えば、亡くなったのが自分の会社の同僚で、喪主がその方の奥様である場合、故人は自分にとっては「同僚」ですが、喪主である奥様から見れば「ご主人様」となります。
したがって、電報の本文では「ご主人様のご逝去を悼み…」といった形で敬称を使用します。
もし、喪主と故人の続柄が分からない場合は、「故〇〇様」のように故人のお名前をそのまま使用するのが最も無難です。
敬称を無理に使おうとして間違えてしまうよりは、お名前を用いる方が丁寧です。
これらの敬称は、お悔やみの電報は縦書きか横書きかという書式に関わらず、必ず守るべきマナーです。
弔電を手配する際には、この敬称のルールを再度確認し、間違いのないように細心の注意を払いましょう。
正しい敬称を使うことで、ご遺族に対して深い配慮と敬意の気持ちを伝えることができます。
お悔やみの電報は縦書きか横書きかで迷った時の注意点
- ➤句読点を使わないのが弔電の基本マナー
- ➤会社名義や連名で送る場合の書き方
- ➤知らないと失礼にあたる忌み言葉とは
- ➤宛名は喪主にするのが一般的
- ➤まとめ:お悔やみの電報は縦書きか横書きかより心が大切
句読点を使わないのが弔電の基本マナー

お悔やみの電報を作成する際、日常の手紙や文章と同じ感覚で句読点(「、」読点、「。」句点)を使ってしまう方がいますが、これは弔電におけるマナー違反とされています。
弔電の本文では、句読点を使用しないのが古くからの慣習です。
これには、いくつかの理由があるとされています。
最も一般的な説は、「儀式が滞りなく、スムーズに進み、無事に終わりますように」という願いが込められているというものです。
文章の途中で区切りを入れる句読点が、物事の流れを中断させることを連想させるため、葬儀という厳粛な儀式においては避けるべきだと考えられてきました。
また、別の説としては、昔の日本の正式な毛筆の書状には句読点を用いる習慣がなかったため、その名残であるとも言われています。
さらに、句読点がないと文章が読みにくいことから、相手への教育的な意味合いを持つと考えられた時代もあり、弔意を示す場では失礼にあたるとされた、という背景もあるようです。
理由はどうであれ、現代においても、弔電では句読点を使わないのが正式なマナーとして定着しています。
では、句読点を使わずに、どのようにして文章を読みやすくすればよいのでしょうか。
その答えは、「空白(スペース)」の活用にあります。
文章を区切りたい場所や、読点を打ちたい場所では、代わりに全角または半角のスペースを一つ入れます。
文末の句点を打ちたい場所では、スペースを入れるか、何もつけずに改行します。
句読点を使った通常の文章例:
「ご尊父様のご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。ご生前の笑顔ばかりが思い出され、胸が締めつけられる思いです。ご遺族の皆様も、さぞご傷心のことと存じますが、どうかご自愛ください。」
句読点を避けた弔電の文章例:
「ご尊父様のご逝去の報に接し 心よりお悔やみ申し上げます
ご生前の笑顔ばかりが思い出され 胸が締めつけられる思いです
ご遺族の皆様も さぞご傷心のことと存じますが どうかご自愛ください」
このように、スペースや改行をうまく使うことで、句読点がなくても十分に読みやすく、かつ丁寧な印象の文章を作成することができます。
NTTなどの電報サービスの文例集は、基本的にこのルールに則って作成されていますので、それを参考にすると良いでしょう。
この句読点に関するルールは、お悔やみの電報は縦書きか横書きかというレイアウトの違いに関係なく適用されます。
普段の文章作成の癖でうっかり使ってしまわないよう、送信前に必ず最終確認を行うことが大切です。
細かな点ではありますが、こうした配慮がご遺族への深い弔意を伝えることに繋がります。
会社名義や連名で送る場合の書き方
弔電は個人として送るだけでなく、会社や部署、あるいは友人グループなど、複数人の名義で送るケースも少なくありません。
このような場合、差出人の書き方に特有のルールがあるため、注意が必要です。
会社名義で送る場合
ビジネス関係で弔電を送る際は、会社名義で送ることが一般的です。
差出人の記載方法にはいくつかのパターンがあります。
- 会社名+代表者名:最も一般的な形式です。会社の公式な弔意として送る場合に用います。「株式会社〇〇 代表取締役 〇〇 〇〇」のように記載します。
- 会社名+部署名+役職名+個人名:故人や喪主と特に親しい関係にあった部署から送る場合に用います。「株式会社〇〇 営業部 部長 〇〇 〇〇」のように、具体的な部署や個人の名前を入れることで、より心のこもった印象になります。
- 部署名一同:部署全体からの弔意として送る場合に用います。「株式会社〇〇 営業部一同」のように記載します。個人名を列挙するのが難しい場合や、部署としてお悔やみを伝えたい場合に適しています。
差出人を記載する際には、会社名や部署名を正式名称で、省略せずに書くのがマナーです。
また、会社の住所や連絡先も忘れずに記載しましょう。ご遺族が後日お礼状などを送る際に必要となります。
連名で送る場合
友人や同僚など、複数人が連名で弔電を送る場合、名前を記載する順番に配慮が必要です。
基本的には、目上の方や年長者から順に、右から左(縦書きの場合)または左から右(横書きの場合)へ記載します。
役職がある場合は、役職の高い人から順に書きます。
役職や年齢に特に差がない友人同士などの場合は、五十音順で記載するのが一般的です。
名前を列挙する場合、人数が多いと読みづらくなってしまうため、一般的には3名程度までとされています。
4名以上になる場合は、代表者1名の名前を記載し、その横(縦書きの場合は下)に「外一同(他一同)」と書き添えるのがスマートな方法です。
もしくは、会社の場合と同様に「〇〇大学 友人一同」のようにグループ名でまとめるのも良いでしょう。
【連名の記載例】
- 3名の場合:山田 太郎 鈴木 次郎 佐藤 三郎
- 4名以上の場合:山田 太郎 外一同
- グループの場合:〇〇サークル 有志一同
連名で送る場合も、代表者の住所や連絡先を明記することを忘れないようにしましょう。
これらの書き方は、お悔やみの電報は縦書きか横書きかに関わらず共通のルールです。
正しい書き方で差出人を記載し、誰からのお悔やみなのかをご遺族に明確に伝えることが大切です。
知らないと失礼にあたる忌み言葉とは

弔電のメッセージを作成する際に、句読点や敬称と並んで細心の注意を払わなければならないのが「忌み言葉(いみことば)」の使用です。
忌み言葉とは、不幸が重なることや、死、苦しみを直接的に連想させるため、弔事の場では避けるべきとされる言葉のことを指します。
悪意がなくとも、うっかり使ってしまうとご遺族の心を傷つけ、大変失礼にあたりますので、必ず確認が必要です。
忌み言葉は、大きく分けて以下の2つの種類があります。
1. 重ね言葉
不幸が「重なる」「繰り返す」ことを連想させるため、使用を避けます。
日常会話で何気なく使っている言葉が多いため、特に注意が必要です。
- 重ね重ね(かさねがさね) → 「加えて」「深く」などに言い換える
- たびたび → 「よく」「いつも」などに言い換える
- ますます → 「さらに」「一段と」などに言い換える
- くれぐれも → 「十分に」「どうぞ」などに言い換える
- 次々、追って → 不幸が続くことを連想させるため使用を避ける
言い換え例:「重ね重ねお悔やみ申し上げます」→「深くお悔やみ申し上げます」
2. 直接的な表現や不吉な言葉
「死」や「苦しみ」を直接的に表現する言葉や、生死に関する不吉な言葉は、より柔らかな表現に言い換えるのがマナーです。
- 死亡、死ぬ → 「ご逝去(ごせいきょ)」「永眠(えいみん)」「他界(たかい)」などに言い換える
- 生きているうち、生きていた頃 → 「ご生前(ごせいぜん)」「お元気でいらした頃」などに言い換える
- 苦しむ → 「ご療養」「闘病」などの言葉も、状況によっては避けた方が良い場合があります。
- 浮かばれない、迷う → 仏教用語で成仏できないことを意味するため避けます。
これらの忌み言葉は、お悔やみの電報は縦書きか横書きかという形式に関係なく、絶対に使わないようにしましょう。
また、宗教によっても特定の忌み言葉があります。
例えば、キリスト教では故人は神のもとに召されると考えられるため、「冥福」「供養」「成仏」といった仏教用語は使用しません。
代わりに、「安らかな眠りにつかれますよう、心よりお祈り申し上げます」といった表現を用います。
ご遺族の宗教が分からない場合は、宗教色のない言葉を選ぶのが最も安全です。
電報を送る前に、作成したメッセージを声に出して読み返し、忌み言葉が含まれていないか、不自然な表現はないかを最終チェックする習慣をつけることを強くお勧めします。
宛名は喪主にするのが一般的
弔電を誰宛に送ればよいのか、というのも迷いやすいポイントの一つです。
お悔やみの電報の宛名は、葬儀を取り仕切る責任者である「喪主(もしゅ)」の方のお名前で送るのが基本です。
葬儀に関する連絡やお香典、弔電などはすべて喪主に集約されるため、宛名を喪主にしておくことで、ご遺族側での管理がしやすくなります。
宛名の書き方は、「(喪主のフルネーム)様」とします。
もし喪主のお名前が分からない場合は、どうすればよいのでしょうか。
訃報の連絡を受けた際に確認するのが最も確実ですが、急なことで聞きそびれてしまったり、確認する術がなかったりする場合もあるでしょう。
そのような場合は、故人のお名前を借りて、以下のように記載します。
【喪主不明の場合の宛名例】
「故 〇〇 〇〇様 ご遺族様」
または
「〇〇家 ご遺族様」
このように記載すれば、喪主がどなたであっても失礼にあたることはありません。
ただし、喪主と面識がない場合でも、できる限り喪主のお名前を確認する努力をするのが望ましい姿勢です。
会社関係の訃報であれば、総務部などに問い合わせれば教えてもらえることが多いです。
もう一つ注意したいのが、故人宛に弔電を送らない、という点です。
お悔やみを申し上げる相手は故人ですが、電報というメッセージを受け取り、読むのはご遺族です。
そのため、宛名を故人のお名前にするのは間違いです。必ず、喪主またはご遺族宛てに送るようにしましょう。
また、弔電を送る斎場やご自宅の住所も正確に記載する必要があります。
特に斎場に送る場合は、同日に複数の葬儀が執り行われている可能性があるため、喪家名(〇〇家)も併記すると、より確実に届けることができます。
- 宛名:喪主のフルネーム。不明な場合は「故 〇〇様 ご遺族様」。
- 送り先:通夜・告別式が行われる斎場またはご自宅の住所。
- 補足:斎場宛の場合は、喪家名(〇〇家)も記載する。
これらの宛名に関するルールは、お悔やみの電報は縦書きか横書きかといった書式に関わらず、必ず守るべき重要なマナーです。
正確な情報を記載し、弔意を確実に届けるための配慮を忘れないようにしましょう。
まとめ:お悔やみの電報は縦書きか横書きかより心が大切

これまで、お悔やみの電報に関するさまざまなマナーや注意点について解説してきました。
お悔やみの電報は縦書きか横書きかという基本的な書式の問題から、台紙の選び方、敬称の使い方、忌み言葉、宛名の書き方まで、覚えるべきルールは数多くあります。
これらの形式やマナーをきちんと守ることは、ご遺族に対して敬意と配慮を示す上で非常に重要です。
しかし、最も忘れてはならないのは、形式以上に、故人を心から偲び、悲しみに暮れるご遺族を慰めたいという「気持ち」そのものです。
どれほど立派な台紙を選び、完璧な文章を作成したとしても、そこに心がこもっていなければ、その弔意は十分に伝わりません。
逆に、多少形式が拙かったとしても、故人との思い出やご遺族への温かい気遣いが感じられる言葉は、きっと深く心に響くはずです。
訃報は突然訪れるものです。
動揺し、悲しむ中で、遠方であったり、やむを得ない事情でどうしても葬儀に参列できない場合に、せめてものお悔やみの気持ちを伝える手段が弔電です。
マナーを気にしすぎるあまり、弔電を送ること自体をためらってしまうのは、本末転倒と言えるでしょう。
この記事で解説した内容は、あなたのその大切な気持ちを、失礼のない、より適切な形で伝えるための道しるべです。
迷ったときは、基本に立ち返り、「丁寧さ」を心がけることが大切です。
例えば、縦書きを選ぶ、信頼できるNTTなどのサービスを利用する、文例を参考にしつつも自分の言葉を少し添える、といった配慮が、あなたの真心を伝えます。
また、弔意を示す方法は弔電だけではありません。
香典や供花を送ることも、お悔やみの気持ちを伝える立派な方法です。
特に、供花は祭壇を飾り、故人への感謝と哀悼の意を形として表すことができます。
中でも、胡蝶蘭はその上品で清楚な佇まいから、お祝いのシーンだけでなく、お悔やみの場にもふさわしい花として選ばれています。
白の胡蝶蘭は、その凛とした美しさで、厳粛な場にふさわしい品格を添え、ご遺族の心を静かに慰めてくれるでしょう。
胡蝶蘭のような格式高い贈り物は、どのようなシーンにでも合い、喜ばれる心遣いとなります。
最終的に、お悔やみの電報は縦書きか横書きかという選択も、その他のマナーも、すべてはあなたの弔意を正しく伝えるための手段です。
一番大切なのは、故人を偲び、ご遺族に寄り添う温かい心です。
その気持ちを胸に、あなたらしい方法でお悔やみを伝えてください。
- ➤お悔やみの電報は縦書きか横書きかで迷ったら縦書きがより丁寧
- ➤横書きは親しい間柄や洋風の台紙に適している
- ➤台紙は故人の人柄や宗教に配慮し落ち着いたデザインを選ぶ
- ➤信頼できるNTTなどの電報サービスを利用すると安心
- ➤弔電の書体は楷書体か明朝体が一般的
- ➤文例集を参考にしつつ自分の言葉を添えると気持ちが伝わる
- ➤敬称は喪主から見た続柄で正しく使い分ける
- ➤本文に句読点「、」「。」は使わずスペースで区切るのがマナー
- ➤「重ね重ね」などの重ね言葉や「死」などの直接的な表現は忌み言葉
- ➤会社名義や連名で送る際は差出人の順序や書き方に注意する
- ➤宛名は葬儀の責任者である喪主にするのが基本
- ➤喪主が不明な場合は「故〇〇様 ご遺族様」と記載する
- ➤形式やマナー以上に故人を偲び遺族を思う心が最も重要
- ➤弔意を示す方法として弔電のほかに供花も有効な選択肢
- ➤品格のある胡蝶蘭はどのようなお悔やみのシーンにもふさわしい贈り物










