
胡蝶蘭についてはコチラもお読みください。
この度は、大切な方を亡くされたご遺族に、心からお悔やみ申し上げます。
故人を偲び、お悔やみの気持ちを伝えるために、お花を贈りたいとお考えのことでしょう。
しかし、どのようなお花を選べば良いのか、特に最近人気のドライフラワーやプリザーブドフラワーは贈っても良いものなのか、迷われる方も少なくありません。
「お悔やみにドライフラワーは失礼にあたるのではないか」という疑問は、故人やご遺族に対して失礼があってはならないと考える、あなたの優しいお心遣いの表れだと思います。
実際のところ、お悔やみのシーンにおけるお花の選び方には、古くからの習わしやマナーが存在します。
この記事では、お悔やみにドライフラワーは失礼とされる理由から、四十九日などの法要における供花のマナー、仏壇にお供えする際の注意点、そしてお悔やみの気持ちを伝えるのにふさわしいお花、特に胡蝶蘭の選び方まで、詳しく解説していきます。
葬儀に参列できない場合や、後から訃報を知った場合など、お花に代わる心のこもった贈り物を探している方にも、きっとお役立ていただける内容です。
お供えとしてプリザーブドフラワーは失礼にあたらないのか、どのような花がタブーとされるのかといった、多くの方が抱く疑問にもお答えします。
故人への敬意と、悲しみの中にいるご遺族の心に寄り添うための、正しい知識とマナーを身につけていきましょう。
- ➤お悔やみにドライフラワーが失礼とされる本当の理由
- ➤プリザーブドフラワーとお悔やみの関係性
- ➤宗教・宗派によるお供え花の考え方の違い
- ➤四十九日や法要など贈るタイミングごとのマナー
- ➤仏壇にお供えする花の正しい選び方
- ➤悲しみの場にふさわしくないタブーの花の種類
- ➤どのようなお悔やみのシーンにも最適な胡蝶蘭の魅力
なぜ、お悔やみにドライフラワーは失礼といわれるのか
- ➤故人への弔いに生花が選ばれる理由
- ➤プリザーブドフラワーに対する宗教上の考え方
- ➤遺族への配慮で最も大切なマナーとは
- ➤仏壇へのお供えで避けるべきこと
- ➤四十九日など贈るタイミングの選び方
故人への弔いに生花が選ばれる理由

お悔やみの場面で、古くから生花が用いられてきたのには、深い理由があります。
それは、花の持つ生命の儚さや移ろいが、人の一生と重ね合わせられてきたからです。
美しく咲き誇り、やがて静かに枯れていく花の姿は、命の尊さや、諸行無常という仏教的な思想をも象徴しています。
みずみずしい生花を供えるという行為は、故人の魂を慰め、新たな旅立ちが安らかであるようにという祈りを込めたものなのです。
また、生花の持つ自然な香りや清らかな見た目は、厳かな場の空気を和ませ、残されたご遺族の心を癒す効果もあると考えられています。
これに対して、ドライフラワーは生花を加工し、水分を抜いて作られたものです。
その姿は、時間が止まった状態、つまり「死」や「停止」を連想させるため、弔いの場にはふさわしくないとされています。
生命感のないドライフラワーは、故人の「死」を直接的に突きつけるような印象を与えかねず、ご遺族の悲しみを増幅させてしまう恐れがあるのです。
もちろん、これは伝統的な価値観に基づく考え方であり、ドライフラワーそのものが悪いわけではありません。
インテリアとしては非常に人気があり、そのアンティークな風合いを好む人も多いでしょう。
しかし、お悔やみという非常にデリケートな場面においては、受け取る側の気持ちを最大限に尊重する必要があります。
伝統や慣習を重んじる方々にとっては、ドライフラワーを供える行為が非常識、あるいは失礼なことと映る可能性が高いという点を、心に留めておくべきでしょう。
特に、ご高齢の方や、地域のしきたりを大切にするご家庭に対しては、誤解を招かないためにも、弔いの気持ちを表す際には生花を選ぶのが最も無難で、心のこもった選択と言えます。
故人への追悼とご遺族への配慮という、お悔やみの本質を考えたとき、生命力あふれる生花こそが、最もふさわしい贈り物となるのです。
プリザーブドフラワーに対する宗教上の考え方
近年、お悔やみの花の選択肢として、プリザーブドフラワーが注目されることが増えてきました。
プリザーブドフラワーは、生花に特殊な加工を施して、長期間その美しさを保てるようにしたものです。
見た目は生花とほとんど変わらず、水やりの手間もかからないため、ご遺族の負担を軽減できるというメリットがあります。
しかし、このプリザーブドフラワーをお悔やみに贈ることについては、様々な意見があり、特に宗教上の観点から慎重な判断が求められます。
まず、仏教の多くの宗派では、先述の通り「諸行無常」の考え方を大切にします。
形あるものはすべて移ろい、変化していくという教えです。
この観点からすると、時が経っても枯れないプリザーブドフラワーは、自然の摂理に反するものと捉えられることがあります。
生花が枯れていく過程こそが命の尊さを教える、と考える伝統的な立場からは、プリザーブドフラワーは供花としてふさわしくないとされる場合があるのです。
一方で、仏教の中でも浄土真宗など一部の宗派では、考え方が少し異なります。
浄土真宗では、亡くなった方はすぐに極楽浄土で仏になると考えられているため、「常花(じょうか)」と呼ばれる金色の蓮の花の造花を仏壇に飾る習慣があります。
これは「極楽浄土に咲く枯れない花」を表現したものであり、この考え方から、プリザーブドフラワーを供えることにも比較的寛容な場合があります。
次に、神道の場合、神様への捧げものとしては、最も生命力に満ちた状態のものが尊ばれます。
そのため、瑞々しい生花や、神聖な植物である榊(さかき)が用いられるのが一般的です。
加工品であるプリザーブドフラワーは、神道のお供えとしてはあまり用いられません。
キリスト教においては、お悔やみの花に対する厳格な決まりは比較的少ないとされています。
故人が好きだった花を贈ることも多く、白を基調としたアレンジメントなどが一般的です。
プリザーブドフラワーについても、絶対にダメという決まりはありませんが、こちらもやはり生花を贈るのが最も一般的で、丁寧な印象を与えます。
結論として、プリザーブドフラワーは、ドライフラワーほど強いタブー視はされていないものの、宗教や宗派、さらにはご家庭の考え方によって、受け取られ方が大きく異なるのが現状です。
もし贈りたいと考える場合は、ご遺族の負担を減らしたいという心遣いを伝えた上で、事前にご意向を確認するのが最も安全な方法と言えるでしょう。
もし確認が難しい状況であれば、どの宗教・宗派でも問題なく受け入れられる生花、特に格式の高い胡蝶蘭などを選ぶのが賢明です。
遺族への配慮で最も大切なマナーとは

お悔やみの気持ちを伝える上で、どのようなお花を選ぶかと同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが、ご遺族の心に寄り添う配慮とマナーです。
大切な方を失い、深い悲しみの中にいるご遺族は、精神的にも肉体的にも大きな負担を抱えています。
その状況を理解し、思いやりのある行動を心がけることが、何よりも大切になります。
まず、お花を贈るタイミングです。
訃報を受けてすぐに駆けつける場合や、お通夜・告別式に持参する場合は別ですが、郵送などで贈る際には、ご遺族が少し落ち着かれる時期を見計らう配慮が求められます。
葬儀の直後は、様々な手続きや弔問客への対応で非常に慌ただしくされています。
そのタイミングで大きなお花が届くと、かえって手間を増やしてしまうことになりかねません。
一般的には、葬儀後から四十九日までの間に贈るのが良いとされています。
次に、お花のサイズやスタイルです。
ご自宅に贈る場合、あまりにも大きなアレンジメントは飾る場所に困らせてしまう可能性があります。
特に最近の住宅事情を考えると、仏壇の周りやリビングに置けるような、控えめで上品なサイズ感が好まれます。
また、香りの強すぎる花は避けるのがマナーです。
ユリなどは代表的な供花ですが、香りが強い品種もあるため、配慮が必要です。
故人が好きだったという特別な理由がない限りは、香りが穏やかな花を選ぶのが無難でしょう。
そして、最も重要なのが、メッセージを添えることです。
お花だけを贈るのではなく、「心よりお悔やみ申し上げます」「安らかなるご冥福をお祈りいたします」といった短い言葉でも構いませんので、必ずお悔やみのメッセージカードを付けましょう。
その際、忌み言葉(「重ね重ね」「くれぐれも」といった不幸が重なることを連想させる言葉や、「死ぬ」「苦しむ」といった直接的な表現)を使わないように注意が必要です。
お悔やみの花は、単なる贈り物ではありません。
故人を偲び、ご遺族を慰めるための、心のコミュニケーションです。
お悔やみにドライフラワーは失礼という考え方の根底にも、この「ご遺族への配慮」があります。
たとえ悪意がなくても、受け取った側が不快に感じたり、悲しい気持ちになったりする可能性のあるものは避ける。
この相手を思いやる気持ちこそが、お悔やみの場で最も大切にすべきマナーと言えるでしょう。
仏壇へのお供えで避けるべきこと
ご自宅へ弔問に伺う際や、法事の際に、仏壇にお花をお供えする機会があります。
仏壇は、故人やご先祖様と心を通わせるための大切な場所です。
だからこそ、お供えするお花にも、守るべきマナーや避けるべきことがあります。
まず、大前提として、ドライフラワーは仏壇へのお供えには適していません。
前述の通り、ドライフラワーは「死んだ花」と見なされることがあり、ご先祖様に対して失礼にあたると考えられています。
仏様にお供えするのは、生命力に満ちた生花が基本です。
常に清らかで、瑞々しい状態を保つことが大切にされます。
プリザーブドフラワーについても、宗派やご家庭の考え方によりますが、伝統を重んじる場合は避けた方が賢明です。
次に、生花の中でも避けるべき種類があります。
- トゲのある花
- 香りの強すぎる花
- 毒のある花
- つる性の植物
トゲのある花
バラやアザミなど、トゲのある花は殺生を連想させるため、仏事ではタブーとされています。もし故人がバラが好きだったなどの理由でどうしても供えたい場合は、必ずトゲを全て取り除いてからお供えするのがマナーです。
香りの強すぎる花
ユリやクチナシ、スイセンなど、香りが非常に強い花は、お線香の香りを妨げると考えられています。また、狭い室内で強い香りが充満すると、気分が悪くなる方もいるため、避けた方が良いでしょう。
毒のある花
彼岸花(曼珠沙華)やスズラン、トリカブトなど、毒性を持つ植物は、仏様にお供えするにはふさわしくありません。特に小さなお子様やペットがいるご家庭では、危険を避ける意味でも絶対に選んではいけません。
つる性の植物
アサガオやクレマチスなどのつる性の植物は、仏壇の飾りつけがしにくいだけでなく、その絡みつく性質から「成仏できない」ことを連想させるとして、嫌われることがあります。
また、お供えした花が枯れてきたら、すぐに新しいものと取り替えることも大切な作法です。
枯れた花をそのままにしておくのは、ご先祖様に対して失礼にあたりますし、衛生的にも良くありません。
仏壇は常に清浄に保つことを心がけ、感謝の気持ちを込めてお世話をすることが、何よりの供養となるのです。
これらの点を踏まえ、仏壇には、菊やカーネーション、トルコギキョウ、そして格式高い胡蝶蘭といった、穏やかで上品な花を選ぶのが最適と言えるでしょう。
四十九日など贈るタイミングの選び方
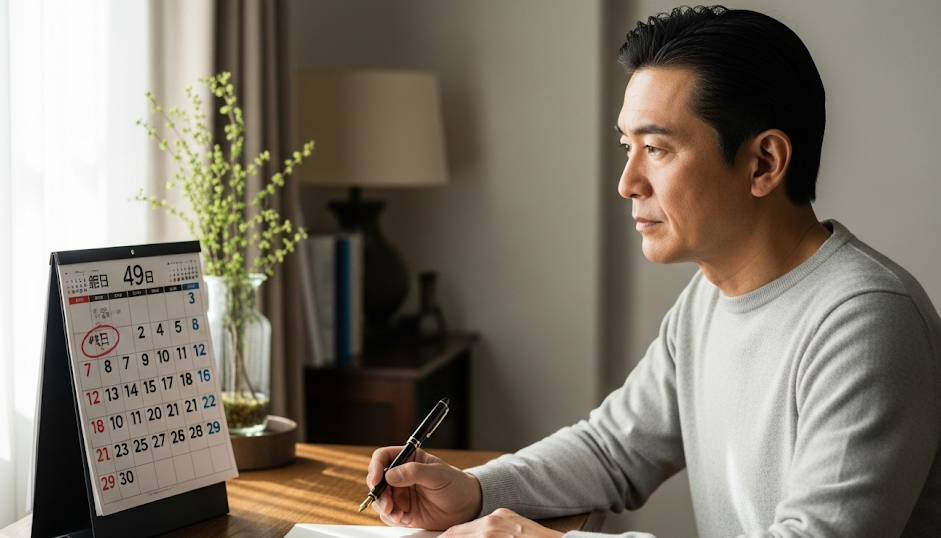
お悔やみの花を贈る際には、そのタイミングも非常に重要です。
ご遺族の状況や、宗教的な儀式の意味合いを理解して、適切な時期に贈ることが、心遣いの表れとなります。
ここでは、代表的なタイミングごとのマナーについて解説します。
お通夜・告別式
訃報を受けてすぐ、お通夜や告別式の会場にお花を贈る場合、これは「供花(きょうか・くげ)」と呼ばれます。
通常は、故人や遺族の名前で飾られる大きなスタンド花が一般的で、葬儀社を通じて手配することが多いです。
個人的に小さなアレンジメントを持参するのは、あまり一般的ではありません。
この段階では、白を基調とした菊やユリ、胡蝶蘭などが用いられます。
葬儀後から四十九日まで
ご遺族のご自宅にお花を贈る場合、最も一般的なのがこの期間です。
葬儀直後の慌ただしさが少し落ち着き、ご遺族が故人を偲び静かに過ごす時間が増える頃です。
この時期に贈る花は「後飾り(あとかざり)の祭壇」や仏壇にお供えされます。
「枕花(まくらばな)」とも呼ばれます。
お花の色合いは、まだ悲しみが深い時期であることを考慮し、白を基調にするのがマナーです。
「白上がり」と呼ばれる、白い花だけでまとめたアレンジメントが最も丁寧です。
少し色を入れる場合でも、淡い紫や青、グリーンなど、控えめで落ち着いた色合いに留めましょう。
四十九日までは、故人の魂がまだこの世とあの世の間を旅している期間とされ、特に手厚く供養するべき大切な時期です。
この期間にお花を贈ることは、ご遺族の心を慰め、故人への弔意を示す上で非常に意味のある行為と言えます。
四十九日法要以降
四十九日を過ぎると、忌明けとなります。
この日を境に、お供えするお花の色合いも少しずつ明るいものを加えていくことが許容されます。
故人が好きだった明るい色の花(ただし、原色などの派手すぎる色は避ける)や、淡いピンク、黄色などを加えたアレンジメントも良いでしょう。
月命日や年忌法要(一周忌、三回忌など)に合わせてお花を贈るのも、故人を忘れずにいるという気持ちが伝わり、ご遺族に喜ばれます。
お花を贈る際には、どのタイミングであっても、事前にご遺族に連絡を一本入れておくと、より丁寧です。
受け取りの日時などを確認することで、ご遺族の負担を減らすことができます。
急な訪問は避け、配送サービスを利用するのが現代的なマナーと言えるでしょう。
タイミングを見極め、相手の状況を思いやった上で行動することが、お悔やみの場面では何よりも大切です。
お悔やみにドライフラワーは失礼との考えがある中での選び方
- ➤悲しみに寄り添う花のアレンジメント
- ➤贈ってはいけないタブーの花の種類
- ➤間違えないための供花の選び方の基本
- ➤どのようなシーンでも喜ばれる胡蝶蘭という選択
- ➤お悔やみにドライフラワーは失礼かを理解し心を伝える
悲しみに寄り添う花のアレンジメント

お悔やみの花を贈る際、ただ花を選んで贈るだけでなく、そのアレンジメントのスタイルにも心を配ることで、より深く弔意を伝えることができます。
悲しみの中にいるご遺族の心に、そっと寄り添うようなアレンジメントを心がけましょう。
色合いの選び方
お悔やみの花の色は、贈る時期によって変わります。
基本となるのは「白」です。
白は純粋、無垢、そして哀悼の意を表す色とされています。
- お通夜~四十九日まで:白上がり(白一色)が最も正式で丁寧です。もし色を加えるなら、淡い紫、青、緑といった寒色系のごく控えめな差し色に留めます。
- 四十九日以降:少しずつ色を加えても良いとされます。故人が好きだった色や、淡いピンク、黄色、水色など、優しく穏やかな色合いを選びます。ただし、赤やオレンジといった鮮やかすぎる色、お祝い事を連想させる色は避けるのがマナーです。
花の種類の選び方
お悔やみのアレンジメントには、日持ちがして、見た目が上品で、香りが控えめな花が好まれます。
代表的な花には、菊(特に白いマム)、ユリ(香りの少ない品種)、トルコギキョウ、カーネーション、そして胡蝶蘭などがあります。
これらの花は、見た目の美しさだけでなく、それぞれが持つ花言葉も弔いの場にふさわしいものが多いです。
例えば、白い菊は「ご冥福をお祈りします」、白いカーネーションは「尊敬」、胡蝶蘭は「清純」といった花言葉を持っています。
アレンジメントのスタイル
ご遺族のご自宅に贈る場合は、そのまま飾れる「アレンジメント」のスタイルが最も親切です。
花瓶を用意する手間をかけさせないための配慮です。
サイズは、飾る場所に困らないよう、大きすぎないものを選びます。
横に広がるタイプよりも、縦にすっと伸びるような、清楚で上品なデザインが良いでしょう。
また、花束で贈る場合は、ご遺族が花瓶に移し替える際に手間がかからないよう、根元の処理をきちんとしておくことが大切です。
最近では、ボックスの中に花を詰めた「ボックスフラワー」も人気ですが、これは少しカジュアルな印象を与える可能性があるため、親しい間柄の方に贈る場合に留めておくのが無難かもしれません。
どのようなスタイルを選ぶにせよ、大切なのは「故人を偲び、遺族を気遣う気持ち」です。
その気持ちが伝わるよう、派手さや奇抜さではなく、控えめで品格のあるアレンジメントを選ぶことが、悲しみの場にふさわしい心遣いと言えるでしょう。
贈ってはいけないタブーの花の種類
良かれと思って選んだ花が、実はマナー違反だった、ということになれば、贈った側も贈られた側も、後味の悪い思いをしてしまいます。
お悔やみの場には、古くからの慣習や縁起担ぎなどから、避けるべきとされるタブーの花が存在します。
ここでは、代表的なものをいくつかご紹介します。
トゲのある花
最も代表的なタブーは、バラやアザミ、サンザシといったトゲのある花です。
トゲは「痛み」や「争い」「殺生」を連想させるため、仏事全般で避けられます。
特にご高齢の方や、伝統を重んじる方にとっては、常識外れと受け取られかねません。
もし故人がバラをこよなく愛していた、というような特別な事情がある場合に限り、トゲを全て丁寧に取り除いた上で贈るという方法もありますが、基本的には避けるべきです。
香りが強すぎる花
ユリ、フリージア、クチナシ、スイセンなどは、非常に香りが強いことで知られています。
花の香りは心を癒すものですが、強すぎるとかえって不快に感じられたり、お線香の香りを邪魔してしまったりすることがあります。
特に、ご遺族の中には、悲しみと心労で体調を崩されている方もいらっしゃいます。
強い香りが頭痛などを引き起こす可能性も考慮し、香りが穏やかな花を選ぶのが優しさです。
ユリを贈りたい場合は、カサブランカなどのオリエンタルリリーではなく、スカシユリやテッポウユリといった、香りが少ないか、ほとんどない品種を選ぶと良いでしょう。
派手な色の花
お悔やみの場は、静かに故人を偲ぶ場所です。
そのため、真っ赤なバラや、鮮やかなオレンジ色のガーベラなど、お祝い事を連想させるような派手な色の花はふさわしくありません。
赤は血を連想させる色でもあるため、特に避けるべき色とされています。
四十九日を過ぎてから少し明るい色を入れる場合でも、あくまで淡く優しい色合いのものを選びましょう。
毒を持つ花
当然のことながら、毒のある植物は贈ってはいけません。
彼岸花(曼珠沙華)、スズラン、トリカブト、水仙(特に球根部分)などがこれにあたります。
仏様や故人に毒を供えるということ自体が失礼にあたりますし、万が一、小さなお子様やペットが誤って口にしてしまう危険性も考えられます。
花が首から落ちる花
椿(つばき)や山茶花(さざんか)は、花が散るときに、花びらが一枚ずつ散るのではなく、花の形を保ったまま首からぽとりと落ちます。
この様子が「斬首」や「落首」を連想させ、縁起が悪いとされているため、お悔やみやお見舞いの際にはタブーとされています。
これらのタブーを知っておくことは、相手への配慮を示す上で非常に重要です。
迷ったときは、花屋さんに「お悔やみ用で」と伝えて相談するのが、最も確実で安心な方法です。
間違えないための供花の選び方の基本

ここまで、お悔やみの花に関する様々なマナーや注意点について解説してきました。
情報量が多く、少し難しく感じられたかもしれません。
そこで、これまでのポイントを整理し、「これさえ押さえておけば間違いない」という供花選びの基本をまとめます。
基本1:花の種類は「生花」を選ぶ
まず、大原則として、お悔やみには「生花」を選びましょう。
お悔やみにドライフラワーは失礼という考え方は、今もなお根強く残っています。
プリザーブドフラワーも便利ですが、受け取る側の考え方によっては歓迎されない可能性もゼロではありません。
どのような相手にも失礼なく、弔意がまっすぐに伝わるのは、生命力あふれる生花です。
基本2:タイミングと色合いを合わせる
贈るタイミングに応じて、ふさわしい色合いを選ぶことが大切です。
- 四十九日前:白上がり(白一色)を基本とする。
- 四十九日後:白を基調に、淡いピンクや黄色、水色などの優しい差し色を加える。
このルールを覚えておけば、大きくマナーを外すことはありません。
基本3:タブーの花を避ける
「トゲのある花」「香りが強すぎる花」「派手な色の花」「毒のある花」は、お悔やみのシーンでは避けるのが無難です。
これらの花は、故人やご遺族に対して失礼にあたる可能性があります。
迷ったら、菊、カーネーション、トルコギキョウ、胡蝶蘭といった定番の花の中から選ぶと安心です。
基本4:スタイルとサイズに配慮する
ご遺族の手間を考え、花瓶がなくてもそのまま飾れる「アレンジメント」スタイルが最も親切です。
サイズは、ご自宅のスペースを考慮し、大きすぎず、品の良いものを選びましょう。
高さがあり、すっきりとしたデザインのものが好まれます。
基本5:メッセージカードを必ず添える
お花だけを贈るのではなく、必ずお悔やみの言葉を記したメッセージカードを添えましょう。
「ご冥福をお祈りいたします」といった定型文でも構いません。
あなたの名前をしっかりと記し、誰からの弔意なのかが明確にわかるようにすることが重要です。
これらの基本を押さえておけば、お悔やみの花選びで大きく失敗することはありません。
しかし、最も大切なのは、故人を悼み、ご遺族の悲しみに寄り添う「心」です。
マナーは、その心を相手に正しく伝えるための手段です。
心を込めて選んだお花は、きっとご遺族の慰めとなるでしょう。
どのようなシーンでも喜ばれる胡蝶蘭という選択
お悔やみの花選びで、もし何を選べば最も失礼がなく、かつ心からの敬意と弔意が伝わるか迷ったなら、自信をもって「胡蝶蘭」をおすすめします。
胡蝶蘭は、お祝いの贈り物として有名ですが、実はお悔やみのシーンにおいても、これ以上ないほどふさわしいお花なのです。
1. 上品で格調高い花姿
蝶が舞うような優美な花姿は、非常に上品で気品があります。
派手さはありませんが、その凛とした佇まいは、静かに故人を偲ぶ厳かな場の雰囲気を壊すことなく、むしろ格調高く彩ってくれます。
色は、清浄な「白」が基本です。
白い胡蝶蘭の花言葉は「清純」であり、故人の清らかな旅立ちを祈る気持ちを表現するのに最適です。
2. 香りがほとんどない
胡蝶蘭には、香りがほとんどありません。
そのため、お線香の香りを邪魔することも、香りに敏感なご遺族に不快感を与えることもありません。
病院やご自宅など、場所を選ばずに安心して贈ることができます。
3. 長い期間美しく咲き続ける
胡蝶蘭は、他の切り花と比べて、非常に花持ちが良いのが特徴です。
環境が良ければ1ヶ月以上、美しい花を咲かせ続けます。
これは、頻繁に花を取り替える手間をご遺族にかけさせない、という大きなメリットになります。
また、長く咲き続ける花の姿は、故人を偲ぶ時間をゆっくりと共有させてくれ、ご遺族の心を長く慰めてくれることでしょう。
4. 宗教・宗派を問わない
特定の宗教的な意味合いが少ないため、仏教、神道、キリスト教など、どのような宗教・宗派のご家庭にも安心して贈ることができます。
この普遍性は、相手の宗教がわからない場合でも失礼にあたる心配がないという、大きな利点です。
5. 世話が簡単
鉢植えの胡蝶蘭は、水やりも頻繁にする必要がなく、管理が非常に簡単です。
心労の多いご遺族にとって、お手入れに手がかからないという点は、見過ごせない優しさと言えます。
お通夜や告別式の供花としてだけでなく、四十九日法要や一周忌、お盆やお彼岸など、あらゆるお悔やみのシーンで胡蝶蘭は選ばれています。
その理由は、見た目の美しさだけでなく、ご遺族の負担を限りなく減らし、心に寄り添うための配慮が詰まったお花だからです。
「お悔やみにドライフラワーは失礼かもしれない」と悩むあなたのその優しい心遣いは、格式高く、あらゆる面で配慮の行き届いた胡蝶蘭を選ぶことで、最も良い形でご遺族に伝わるはずです。
お悔やみにドライフラワーは失礼かを理解し心を伝える

この記事を通じて、お悔やみにドライフラワーは失礼とされる背景や、お供えの花に関する様々なマナーについてご理解いただけたかと思います。
結論として、伝統や慣習を重んじる日本では、やはりお悔やみの贈り物としてドライフラワーを選ぶのは避けるべき、というのが一般的な見解です。
その根底にあるのは、「生」と「死」に対する考え方、そして何よりも「残されたご遺族の気持ちへの配慮」です。
ドライフラワーが「命の終わり」や「停止」を連想させるのに対し、生花は「命の尊さ」や「魂の再生」を象徴します。
この違いが、弔いの場におけるふさわしさを大きく左右するのです。
また、プリザーブドフラワーについても、その利便性から選ばれることが増えてはいますが、宗教や個人の価値観によっては受け入れられない場合もある、ということを心に留めておく必要があります。
大切なのは、流行りや自分の好みで選ぶのではなく、相手がどう感じるかを第一に考える姿勢です。
お悔やみの花は、あなたの弔意を代弁してくれる、いわば「言葉のかわり」となる存在です。
だからこそ、誤解の余地がなく、敬意と哀悼の気持ちがまっすぐに伝わるものを選ばなければなりません。
色合い、花の種類、贈るタイミング、そしてメッセージカード。一つひとつのマナーを守ることが、あなたの深い思いやりを形にします。
そして、もしあなたが究極の選択として、どのような相手にも、どのようなシーンでも、心からの敬意を示し、ご遺族に喜ばれる贈り物をしたいと考えるなら、胡蝶蘭が最もふさわしい選択肢となるでしょう。
その気品、花持ちの良さ、香りのなさ、世話の手軽さは、悲しみの中にいる相手への最大限の配慮を体現しています。
お悔やみにドライフラワーは失礼にあたるのか、という問いへの答えを深く理解し、故人への最後の贈り物として、そしてご遺族の心を癒す一助として、最も心のこもったお花を選んでいただければ幸いです。
- ➤お悔やみにドライフラワーは失礼と考えるのが一般的
- ➤ドライフラワーは「死」や「停止」を連想させるため
- ➤弔事には命の尊さを示す「生花」が基本
- ➤プリザーブドフラワーも宗派や考え方により避けるべき場合がある
- ➤お悔やみのマナーで最も大切なのは遺族への配慮
- ➤四十九日までは白い花を基調にするのが丁寧
- ➤四十九日以降は淡く優しい色を加えても良い
- ➤トゲや強い香り、毒のある花はタブー
- ➤そのまま飾れるアレンジメントが親切
- ➤サイズは大きすぎず品の良いものを選ぶ
- ➤お悔やみの言葉を記したメッセージカードを必ず添える
- ➤宗教宗派を問わず贈れるのが胡蝶蘭の利点
- ➤胡蝶蘭は上品で花持ちが良く香りが少ない
- ➤世話が簡単な胡蝶蘭は遺族の負担を軽減する
- ➤迷った時は格式高い胡蝶蘭を選べば間違いない










