
胡蝶蘭についてはコチラもお読みください。
突然の訃報に接し、故人を偲ぶ気持ちをどのように伝えれば良いか、心を悩ませている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特に、お悔やみの品として一般的なお線香ではなく、他のものを贈りたいと考えたとき、「お悔やみに線香以外の品物を贈るのは失礼にあたらないだろうか」「どのような品物を選べば遺族に負担をかけずに気持ちを伝えられるのだろう」といった疑問や不安がよぎることもあるでしょう。
宗教上の理由や、ご遺族の状況を配慮して、あえて線香以外の贈り物を選びたいというケースは少なくありません。
また、故人が好きだったものを供えたいという温かい気持ちから、お菓子や飲み物、美しい花などを検討することもあるかもしれません。
しかし、贈り物を選ぶ際には、タイミングや相場、守るべきマナー、そして贈ってはいけないNGな品など、知っておくべき点がいくつかあります。
心を込めて選んだ贈り物が、かえってご遺族の迷惑になってしまっては本末転倒です。
この記事では、お悔やみに線香以外の品物を贈る際の基本的なマナーから、具体的な品物の選び方、添えるメッセージの文例まで、あなたの疑問や不安を解消するために必要な情報を網羅的に解説します。
特に、どのようなシーンでも失礼にあたらず、故人への敬意と遺族への慰めの気持ちを格調高く伝えられる贈り物として、胡蝶蘭の魅力についても詳しくご紹介します。
この記事を読み終える頃には、自信を持って、故人を偲び、ご遺族の心に寄り添うことができる、心のこもった贈り物を選べるようになっているはずです。
- ➤お悔やみに線香以外の品物を贈ることが失礼にあたらない理由
- ➤贈り物を選ぶ際に知っておくべき基本的なマナーや相場
- ➤宗教や宗派によって異なる贈り物の考え方
- ➤避けるべきNGな品物の具体的な例
- ➤お供え物を贈るのに最適なタイミング
- ➤線香以外でおすすめの具体的な贈り物のアイデア
- ➤気持ちが伝わるお悔やみメッセージの書き方
お悔やみに線香以外の品物を選ぶ際の基本マナー
- ➤そもそも線香以外の品物を贈っても失礼ではないか
- ➤贈り物を選ぶ際に知っておきたい基本的なマナー
- ➤相手に配慮した贈り物の金額相場
- ➤宗教や宗派による贈り物の違い
- ➤贈ってはいけないNGな品物とは
- ➤お供え物を贈るのに適したタイミング
そもそも線香以外の品物を贈っても失礼ではないか

お悔やみの気持ちを伝える際、多くの方がまず思い浮かべるのがお線香かもしれません。
しかし、お悔やみに線香以外の品物を贈ることは、決して失礼にはあたりません。
むしろ、故人やご遺族の状況を深く配慮した、思慮深い選択となるケースが多々あります。
なぜなら、お線香を贈ることが必ずしも適切でない場合があるからです。
例えば、キリスト教や神道など、仏教以外の宗教ではお線香を焚く習慣がありません。
そのようなご家庭にお線香を贈ってしまうと、かえって相手を困惑させてしまう可能性があります。
また、仏教のご家庭であっても、最近では住宅事情から煙や香りを気にされる方も増えています。
小さな子供やペットがいるご家庭、あるいはアレルギーをお持ちの方がいる場合、お線香の香りが負担になることも考えられるでしょう。
さらに、他の方からもたくさんのお線香が届いてしまい、使いきれずに持て余してしまうということも少なくありません。
こうした背景から、ご遺族の宗教や生活環境を思いやり、あえて線香以外の品物を選ぶことは、非常に細やかな心遣いの表れと言えます。
故人が生前好きだったお菓子や飲み物、心を癒す美しいお花など、お線香以外の贈り物は、ご遺族にとっても故人を偲ぶきっかけとなり、温かい気持ちを受け取ることができるでしょう。
大切なのは、形式にこだわることよりも「故人を悼み、遺族を気遣う」という真心です。
その気持ちが根底にあれば、お線香以外の贈り物であっても、あなたの弔意は必ずや相手の心に届くはずです。
不安に思う必要はありませんので、自信を持って、相手に寄り添った品物を選んでいきましょう。
贈り物を選ぶ際に知っておきたい基本的なマナー
お悔やみの品を贈る際には、相手に失礼のないよう、いくつかの基本的なマナーを押さえておくことが重要です。
心を込めて選んだ贈り物が、マナー違反によって意図せず相手を不快にさせてしまうことがないよう、事前に確認しておきましょう。
掛け紙(のし)の選び方
お悔やみの贈り物には、慶事で使われる「のし(熨斗)」がついていない「掛け紙」を使用します。
水引は、二度と繰り返したくないという意味を込めて「結び切り」を選びます。
色は、黒白または双銀のものが一般的ですが、関西地方などでは黄白の水引が使われることもあります。
表書きは、贈るタイミングによって異なります。
- 四十九日より前:「御霊前」と書くのが一般的です。ただし、浄土真宗の場合は、亡くなるとすぐに仏様になると考えられているため、時期を問わず「御仏前」を使用します。
- 四十九日以降:「御仏前」と書きます。神式の場合は「御玉串料」、キリスト教の場合は「御花料」となります。
もし相手の宗派が分からない場合は、「御供」や「御供物」とすれば、どの宗教・宗派でも使うことができるため安心です。
名前は、水引の下にフルネームで、薄墨で書くのが正式なマナーとされています。
薄墨は、悲しみの涙で墨が薄まったことを表すためです。
包装の仕方
包装紙は、白黒やグレー、紫など、地味で落ち着いた色合いのものを選びます。
掛け紙の掛け方には、品物に直接掛けてから包装する「内のし」と、包装紙の上から掛ける「外のし」があります。
お悔やみの場合は、誰からの贈り物かすぐに分かるように「外のし」で贈るのが一般的です。
特に郵送する場合は、配送中に掛け紙が汚れたり破れたりするのを防ぐために「内のし」を選ぶこともあります。
贈り物の渡し方
直接弔問に伺う場合は、玄関先で挨拶を済ませた後、お渡しするのがマナーです。
「心ばかりですが、御仏前(御霊前)にお供えください」といった言葉を添えて、相手が正面になるように向きを変えて両手で渡します。
風呂敷に包んで持参した場合は、風呂敷から出して渡しましょう。
遠方であったり、ご遺族の都合を考慮したりして郵送する場合は、品物だけを送るのではなく、必ずお悔やみの手紙を添えることが大切です。
手紙を添えることで、より丁寧に弔意を伝えることができます。
これらのマナーは、相手への敬意と配慮を示すためのものです。
難しく考えすぎず、故人を偲び、ご遺族をいたわる気持ちを大切に行動すれば、きっとその想いは伝わるでしょう。
相手に配慮した贈り物の金額相場
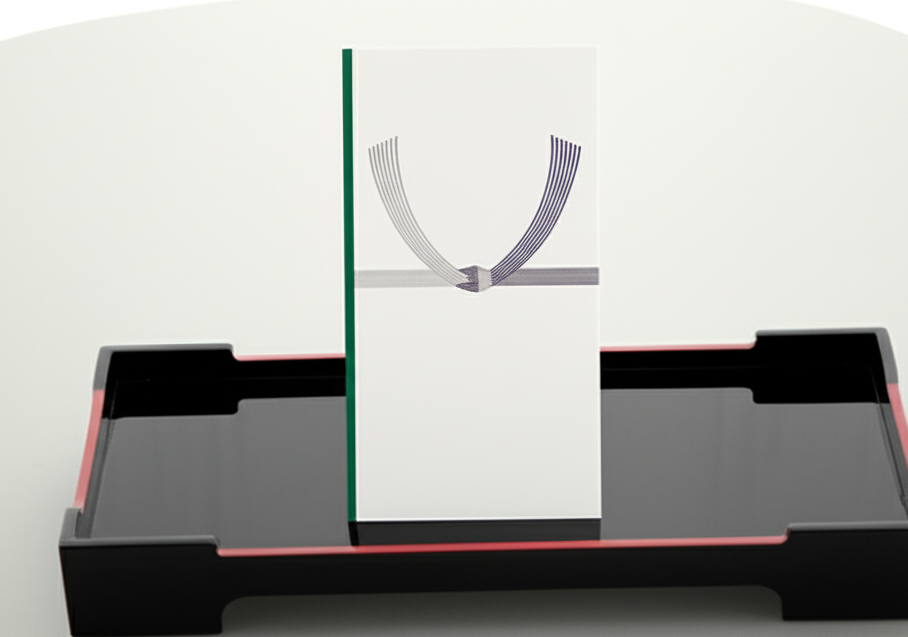
お悔やみに線香以外の品物を贈る際、多くの方が悩むのが金額の相場ではないでしょうか。
高すぎても相手に気を遣わせてしまいますし、安すぎても失礼にあたるのではないかと心配になるものです。
ここでは、相手との関係性を考慮した一般的な金額相場について解説します。
一般的な金額の目安
お悔やみの贈り物の金額相場は、一般的に3,000円から10,000円程度とされています。
これは香典とは別に品物を贈る場合の目安です。
もし香典を包むのであれば、その金額とのバランスを考える必要があります。
香典とお供え物の両方を贈る場合は、合計金額が相場から大きく外れないように調整しましょう。
例えば、5,000円の香典を包むなら、お供え物は3,000円程度の品物にするなど、相手に過度な負担を感じさせない配慮が大切です。
故人との関係性による相場の違い
金額は、故人やご遺族との関係性の深さによって変動します。
以下に、関係性別の相場を表にまとめました。
| 故人との関係性 | 金額相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 親・兄弟姉妹 | 10,000円~30,000円 | 特に親しい間柄のため、相場は高めになります。 |
| 祖父母・親戚 | 5,000円~10,000円 | 生前の付き合いの深さによって調整します。 |
| 友人・知人 | 3,000円~10,000円 | 親しさの度合いによりますが、5,000円前後が一般的です。 |
| 会社関係者(同僚・部下) | 3,000円~5,000円 | 連名で贈る場合は、一人あたりの負担額を考慮します。 |
| 会社関係者(上司) | 5,000円~10,000円 | 目上の方なので、少し高めに設定することが多いです。 |
最も大切なのは、金額の大小よりも、故人を偲び、ご遺族をいたわる気持ちです。
相場はあくまで目安として捉え、ご自身の経済状況や相手との関係性を踏まえて、無理のない範囲で心のこもった品物を選びましょう。
高価なものを贈ることが、かえってご遺族に香典返しの負担をかけてしまうこともあります。
相手の立場に立って考える「心遣い」こそが、最高の贈り物と言えるでしょう。
宗教や宗派による贈り物の違い
日本におけるお悔やみの習慣は、仏教の影響を強く受けていますが、実際にはさまざまな宗教・宗派が存在します。
故人やご遺族が信仰する宗教によって、お供え物の考え方やマナーは大きく異なります。
良かれと思って選んだ品物が、相手の宗教の教えにそぐわないという事態を避けるためにも、基本的な違いを理解しておくことが大切です。
仏式(仏教)
最も一般的なのが仏式です。
仏教では、故人は四十九日の旅を経て仏様になると考えられています。
お供え物は、この旅の間の食事や、仏様への捧げものという意味合いがあります。
線香、ろうそく、お花、果物、お菓子などが定番です。
ただし、前述の通り、浄土真宗では亡くなるとすぐに極楽浄土へ行くとされているため、「御霊前」ではなく「御仏前」の表書きを用いるなど、同じ仏教内でも宗派による違いがあります。
もし宗派が不明な場合は、どの宗派でも使える「御供」とするのが無難です。
神式(神道)
神道では、人は亡くなると家の守り神になると考えられています。
お供え物は「神饌(しんせん)」と呼ばれ、お米、お酒、塩、水、餅、海の幸、山の幸などが供えられます。
仏教で用いられる線香やろうそくは基本的に使いません。
したがって、神式のご家庭へのお悔やみで、お悔やみに線香以外の品物を選ぶのは非常に理にかなった選択です。
お菓子や果物、日持ちのする食品などが喜ばれます。
表書きは「御玉串料(おたまぐしりょう)」や「御榊料(おさかきりょう)」、「御神前」とします。
水引は黒白か双銀の結び切りを用います。
キリスト教式
キリスト教には、そもそも「お供え」という概念がありません。
故人は神様のもとで安らかに過ごしていると考えられており、食べ物などを供える習慣はないのです。
そのため、お悔やみの気持ちを表す際には、品物ではなく「御花料」として現金を包むか、生花を贈るのが一般的です。
特に、白いユリやカーネーション、胡蝶蘭などの生花が好まれます。
十字架や蓮の花が描かれた不祝儀袋は避け、無地の白封筒か、キリスト教用の十字架やユリの花が描かれたものを使用します。
表書きは「御花料」とし、水引のないものを選びます。
どうしても品物を贈りたい場合は、ご遺族が消費できるお菓子や焼き菓子などが良いでしょう。
- 仏式:線香、ろうそく、花、果物、お菓子など。表書きは「御霊前」「御仏前」。
- 神式:お酒、果物、お菓子、日持ちする食品など。線香は使わない。表書きは「御玉串料」。
- キリスト教式:生花が基本。食べ物などのお供えはしない。表書きは「御花料」。
このように、宗教によってマナーは大きく異なります。
相手の宗教が分からない場合は、ご遺族に直接尋ねるのは避け、共通して失礼にあたらないお花やお菓子を選ぶのが最も賢明な選択と言えるでしょう。
贈ってはいけないNGな品物とは

お悔やみの気持ちを伝える贈り物ですが、中には不祝儀の場にふさわしくないとされる「NGな品物」が存在します。
良かれと思って選んだものが、実はマナー違反だったということを避けるためにも、基本的なタブーをしっかりと押さえておきましょう。
四つ足生臭もの(肉や魚)
殺生を連想させる肉や魚などの生鮮食品は、お悔やみの贈り物としては最も避けなければならない品物です。
これらは「四つ足生臭もの」と呼ばれ、仏教の教えに反するとされています。
ハムやソーセージ、魚の干物などの加工品も同様に含まれるため注意が必要です。
故人が生前好きだったとしても、お供え物として贈るのはマナー違反となります。
慶事を連想させる品物
お祝い事を連想させる品物もタブーです。
- お酒(日本酒やビールなど):神道ではお供え物とされますが、一般的にはお祝いの席で飲まれることが多いため、避けた方が無難です。ただし、故人が非常にお酒好きで、ご遺族からリクエストがあった場合などは例外です。
- 昆布や鰹節:「よろこぶ」「勝つ男武士」などの語呂合わせから、結納品など慶事に使われる縁起物です。お悔やみの場にはふさわしくありません。
- 紅白などのおめでたい色の品物:パッケージや中身の色が紅白や金銀など、おめでたい配色のものは避けましょう。
香りの強いもの
香りが強すぎる花や、香りのきついお香、アロマグッズなども配慮が必要です。
ご遺族の中には香りが苦手な方や、アレルギーをお持ちの方がいるかもしれません。
また、ご自宅にたくさんのお花やお供え物が集まっている場合、様々な香りが混ざってしまい、かえって不快に感じさせてしまう可能性もあります。
花を贈る際は、香りが穏やかな品種を選ぶようにしましょう。
現金や商品券(目上の方へ)
現金(香典)は一般的ですが、商品券やギフトカードは避けた方が良いとされています。
金額がはっきりと分かってしまうため、特に目上の方に対しては「生活の足しにしてください」という意味に取られかねず、失礼にあたる可能性があります。
何を贈るか迷った場合は、品物を選ぶか、現金で香典を包むようにしましょう。
これらのNGな品物を避けることは、ご遺族への最低限の配慮です。
選ぶ際には「消えもの」と呼ばれる、食べたり使ったりしてなくなるものが良いとされています。
お菓子や飲み物、あるいは質の良いタオルなどが定番です。
迷ったときは、この「消えもの」の原則を思い出してみてください。
お供え物を贈るのに適したタイミング
お悔やみの品を贈るタイミングは、早すぎても遅すぎてもご遺族の負担になる可能性があります。
相手の状況を考慮し、適切な時期を見計らって贈ることが、心遣いの表れとなります。
ここでは、贈るタイミングについて、いくつかのケースに分けて解説します。
訃報を受けてすぐ(通夜・葬儀)
訃報を受けてすぐに弔問に伺う場合、香典を持参するのが一般的です。
この際、香典とは別にお供え物を持参しても問題ありません。
ただし、ご遺族は非常に慌ただしく、心身ともに疲弊している時期です。
かさばるものや、日持ちのしない生菓子などは、かえって負担をかけてしまう可能性があります。
もし持参するのであれば、個包装で日持ちのするお菓子や、そのまま飾れるアレンジメントフラワーなどが良いでしょう。
葬儀後から四十九日まで
葬儀に参列できなかった場合や、後から訃報を知った場合は、この期間に贈るのが一般的です。
ご遺族は、故人が亡くなった日から七日ごとに法要を営み、故人の冥福を祈ります。
この時期は、祭壇にお供え物が飾られていることが多いため、贈り物が届いても受け入れてもらいやすいでしょう。
郵送で贈る場合は、四十九日の法要に間に合うように、遅くとも法要の1週間前までには届くように手配するのが望ましいです。
四十九日法要以降
四十九日を過ぎてから訃報を知るケースもあります。
その場合は、できるだけ早くお悔やみの気持ちを伝えることが大切です。
「遅ればせながら」という言葉を添えて、お悔やみの手紙と品物を贈りましょう。
一周忌や三回忌などの法要のタイミングで贈るのも良い方法です。
法要の案内状が届いた場合は、法要の数日前から前日までに届くように手配します。
喪中見舞いとして贈る
年末が近づき、喪中はがきで初めて訃報を知ることもあります。
この場合は「喪中見舞い」としてお悔やみの品を贈ります。
年が明けて松の内(1月7日頃)が過ぎてから、「寒中見舞い」として贈る方法もあります。
この場合、お悔やみの品であることが分かるように、掛け紙は「御供」とし、お悔やみの手紙を添えるのが丁寧な対応です。
- 通夜・葬儀:持参する場合は、かさばらず日持ちするものを選ぶ。
- 葬儀後~四十九日まで:最も一般的なタイミング。郵送なら法要の1週間前までに。
- 四十九日以降:訃報を知り次第、できるだけ早く贈る。一周忌などの法要に合わせるのも良い。
- 喪中見舞い:喪中はがきで知った場合に贈る。年末~年明けに届ける。
どのタイミングで贈るにしても、ご遺族の気持ちや状況を最優先に考えることが何よりも重要です。
事前に電話などで都合を伺うのも一つの方法ですが、長電話は避け、手短に用件を伝える配慮を忘れないようにしましょう。
故人を偲ぶ気持ちが伝わるお悔やみに線香以外の贈り物
- ➤日持ちするお菓子や故人が好きだった食べ物
- ➤心が和らぐ胡蝶蘭などのお花やプリザーブドフラワー
- ➤故人が愛したお茶やコーヒーなどの飲み物
- ➤優しい光を灯す絵ろうそくやアロマキャンドル
- ➤品物に添えるお悔やみメッセージの書き方
- ➤まとめ:お悔やみに線-香以外の品物で大切なこと
日持ちするお菓子や故人が好きだった食べ物

お悔やみに線香以外の贈り物として、最も手軽で選ばれやすいのがお菓子や食べ物です。
これらは「消えもの」であり、ご遺族に後々までの負担をかけにくいという利点があります。
選ぶ際には、いくつかのポイントを押さえることで、より心のこもった贈り物になります。
日持ちと個包装が基本
お供え物はすぐに消費されるとは限りません。
ご遺族が落ち着いたタイミングで召し上がったり、弔問客に分けたりすることを考慮すると、最低でも1週間以上、できれば2週間から1ヶ月程度日持ちするものが理想的です。
また、大勢で分けやすいように、一つひとつ個別に包装されているものが大変喜ばれます。
切り分ける手間が省け、衛生的に管理できるため、ご遺族の負担を軽減できます。
- 焼き菓子:クッキー、マドレーヌ、フィナンシェ、バームクーヘンなど。
- 和菓子:おせんべい、おかき、カステラ、どら焼き、羊羹など。
- ゼリーや水ようかん:常温で保存でき、喉越しが良いため、ご年配の方にも喜ばれます。
ケーキなどの生菓子は、日持ちがしないうえ、冷蔵保存が必要になるため、避けた方が無難です。
故人が好きだったものを贈る際の配慮
故人が生前好きだったお菓子や食べ物を贈ることは、故人を偲ぶ気持ちが伝わる素晴らしい選択です。
ご遺族も「〇〇さんは、これが好きだったね」と、故人との思い出を語り合うきっかけになるかもしれません。
ただし、この場合もいくつか注意点があります。
まず、日持ちや個包装といった基本的なポイントは守りましょう。
また、あまりに奇抜なものや、ご遺族が食べられない可能性があるものは避けるべきです。
例えば、アレルギーの原因となりやすいナッツ類が多く含まれるものや、非常に甘いものなどは、贈る前にご遺族の状況をそれとなく確認できるとより安心です。
あくまでお供え物であり、ご遺族が召し上がることを前提に、その配慮を忘れないようにしましょう。
パッケージのデザインにも気を配る
中身だけでなく、パッケージのデザインも重要です。
お悔やみの品であるため、赤や金などのおめでたい色や、派手なデザインのものは避けます。
白や緑、紫、紺といった落ち着いた色合いで、上品なデザインのものを選ぶのがマナーです。
お菓子を選ぶことは、故人への思いとご遺族への配慮を同時に示すことができる行為です。
これらのポイントを参考に、相手の心に寄り添う一品を選んでみてください。
心が和らぐ胡蝶蘭などのお花やプリザーブドフラワー
お悔やみの気持ちを伝える贈り物として、お花は古くから選ばれてきました。
その中でも、格式高く、どのようなシーンにもふさわしいのが胡蝶蘭です。
ここでは、なぜ胡蝶蘭がお悔やみの贈り物として最適なのか、その理由と選び方について詳しく解説します。
胡蝶蘭がお悔やみに最適な理由
胡蝶蘭がお祝い事だけでなく、お悔やみの場にも選ばれるのには、明確な理由があります。
- 上品で格調高い見た目:蝶が舞うような優美な花の姿は、故人への深い敬意と哀悼の意を表すのにふさわしい品格を備えています。祭壇を荘厳に彩り、厳かな雰囲気を演出します。
- 「純粋な愛」「あなたを愛します」という花言葉:白い胡蝶蘭の花言葉は、故人への変わらぬ愛情や、清らかな追悼の気持ちを表現するのにぴったりです。
- 香りと花粉がほとんどない:香りが強い花は避けられる傾向にありますが、胡蝶蘭は香りがほとんどありません。また、花粉も飛散しにくいため、アレルギーの心配が少なく、病院やご自宅など、場所を選ばずに贈ることができます。
- 手入れが簡単で花持ちが良い:胡蝶蘭は生命力が強く、水やりの頻度も少ないため、ご遺族に手入れの負担をかけません。環境が良ければ1ヶ月以上美しい花を咲かせ続けるため、故人を偲ぶ時間が長く続きます。
- 宗教・宗派を問わない:お花は、仏教、神道、キリスト教など、ほとんどの宗教・宗派で受け入れられる普遍的な贈り物です。相手の宗派が分からない場合でも安心して贈ることができます。
これらの理由から、胡蝶蘭はお悔やみに線香以外の贈り物を探している方にとって、最も間違いのない選択肢の一つと言えるでしょう。
胡蝶蘭の選び方(色・サイズ・相場)
お悔やみ用に胡蝶蘭を選ぶ際は、色やサイズに配慮が必要です。
| 項目 | 選び方のポイント |
|---|---|
| 色 | 基本は「白」を選びます。白は清浄無垢な色であり、追悼の意を表すのに最もふさわしいとされています。四十九日を過ぎてからは、故人が好きだった色として、淡いピンクやリップ(中心が赤いもの)などを選ぶこともあります。 |
| サイズ・本数 | ご自宅に贈る場合は、場所を取らない「ミディ胡蝶蘭」や3本立てのものが適しています。葬儀会場など広いスペースに贈る場合は、見栄えのする大輪の3本立てや5本立てが選ばれます。本数は割り切れない奇数が良いとされています。 |
| 相場 | 個人で贈る場合は10,000円~20,000円、法人として贈る場合は20,000円~30,000円が相場です。ミディ胡蝶蘭であれば、10,000円以下でも上品なものを見つけられます。 |
プリザーブドフラワーという選択肢
生花の世話が難しい場合や、より長く飾ってもらいたいという場合には、プリザーブドフラワーも良い選択です。
生花を特殊加工したもので、水やりの必要がなく、美しい状態を数年間保つことができます。
こちらも、白や紫、青を基調とした落ち着いた色合いのアレンジメントを選びましょう。
故人を偲ぶ気持ちを、美しく格調高い形で伝えたいとき、胡蝶蘭は最高のメッセンジャーとなってくれるはずです。
故人が愛したお茶やコーヒーなどの飲み物

お菓子と同様に、お茶やコーヒー、ジュースなどの飲み物も、お悔やみの贈り物としてよく選ばれる品物です。
これらも「消えもの」であり、ご遺族が日々の生活の中で消費しやすいため、負担になりにくいというメリットがあります。
故人が生前好んで飲んでいたものを贈れば、ご遺族も故人を偲びながら、ほっと一息つく時間を持つことができるかもしれません。
ご遺族が消費しやすいものを選ぶ
飲み物を贈る際に最も大切なのは、ご遺族の家族構成や好みを考慮することです。
弔問客へのおもてなしにも使えるため、様々な人が楽しめるものが喜ばれます。
- 日本茶:緑茶やほうじ茶など、普段から飲み慣れているものが良いでしょう。急須がなくても淹れられるティーバッグタイプは手軽で重宝されます。
- コーヒー:一杯ずつ淹れられるドリップバッグのセットは、来客時にも便利で人気があります。様々な種類の詰め合わせも楽しいかもしれません。
- 紅茶:香りやフレーバーが強すぎない、アールグレイやダージリンなどの定番のものが無難です。こちらもティーバッグタイプが便利です。
- ジュース:お子様がいるご家庭には、果汁100%のジュースの詰め合わせも喜ばれます。常温で保存できる瓶や紙パックのものを選びましょう。
故人の好みを反映させる
もし故人が毎日コーヒーを飲むのが習慣だった、特定のお茶の銘柄が好きだった、というようなエピソードを知っていれば、それを贈るのは非常に心のこもった選択です。
「生前、〇〇様がこちらのコーヒーを愛飲されていると伺いましたので」といったメッセージを添えれば、あなたが故人を大切に想っていた気持ちがより一層伝わります。
ただし、あまりに珍しいものや、特別な淹れ方が必要なものは避け、誰もが気軽に楽しめるものを選ぶ配慮も必要です。
パッケージと保存方法に注意
お菓子と同様に、パッケージは落ち着いたデザインのものを選びます。
また、常温で長期間保存できることが重要です。
冷蔵や冷凍が必要なものは、ご遺族の冷蔵庫のスペースを圧迫してしまうため避けましょう。
飲み物は、ご遺族が悲しみの中で過ごす日々に、ささやかな安らぎの時間を提供できる贈り物です。
相手を思いやる気持ちを込めて、最適な一品を選んでみてください。
優しい光を灯す絵ろうそくやアロマキャンドル
火を灯すという行為は、故人の冥福を祈り、心を静める時間を与えてくれます。
お線香の代わりとして、美しい絵柄が描かれた「絵ろうそく」や、優しい香りの「アロマキャンドル」を贈るのも、心のこもった選択です。
これらは、仏壇に手を合わせる時間を、より穏やかで特別なものにしてくれるでしょう。
絵ろうそくの魅力
絵ろうそくは、ろうそくの側面に季節の花や植物などの美しい絵柄が手描きされたものです。
火を灯すと絵柄が浮かび上がり、幻想的で優しい光を放ちます。
特に、生花を供えることが難しい冬場などに、「花の代わり」としてお供えされてきた歴史があります。
蓮の花や桔梗、菊など、仏事にふさわしい落ち着いた絵柄のものを選ぶと良いでしょう。
故人が好きだった花の絵柄を選ぶのも、故人を偲ぶ気持ちが伝わり素敵です。
火を灯さずに、ただ飾っておくだけでも仏壇を華やかに彩ってくれます。
アロマキャンドルを選ぶ際の注意点
優しい香りは、悲しみに沈む心を癒す効果があると言われています。
そのため、アロマキャンドルも選択肢の一つとなります。
しかし、香りについては配慮が必要です。
前述の通り、ご遺族の中には香りが苦手な方やアレルギーを持つ方がいる可能性を忘れてはいけません。
もしアロマキャンドルを贈る場合は、香りが強すぎず、誰もが心地よいと感じるような自然な香りを選ぶことが絶対条件です。
- ラベンダー:リラックス効果が高いことで知られています。
- 白檀(サンダルウッド):お香にも使われる、心を落ち着かせる香りです。
- カモミール:安らぎを与える優しい香りです。
フローラル系やシトラス系でも、香りが控えめなものを選びましょう。
また、煙の少ない植物性のワックス(ソイワックスなど)で作られたキャンドルを選ぶのも、細やかな配慮と言えます。
火を使う贈り物としての心遣い
ろうそくやキャンドルは火を使う品物です。
そのため、安全に使えるよう、燭台(キャンドルホルダー)とセットで贈ると、より親切です。
また、メッセージカードに「火の元には十分お気をつけください」といった一言を添える心遣いも大切です。
ろうそくの灯りは、故人への道を照らし、遺された人々の心を温めると言われています。
ご遺族が故人と静かに対話する時間に寄り添える、そんな思慮深い贈り物になるでしょう。
品物に添えるお悔やみメッセージの書き方

お悔やみの品物を贈る際、特に郵送する場合は、必ずお悔やみのメッセージを添えるのがマナーです。
短い文章であっても、手紙があるのとないのとでは、ご遺族の受け取る印象が大きく異なります。
ここでは、心を込めたメッセージを書くためのポイントと、すぐに使える文例をご紹介します。
メッセージを書く際の基本マナー
お悔やみ状には、いくつかの決まりごとがあります。
失礼にあたらないよう、以下の点を守りましょう。
- 簡潔に書く:ご遺族は心身ともにお疲れの状態です。長文は避け、簡潔にお悔やみの気持ちを伝えます。
- 忌み言葉を避ける:不幸が重なることを連想させる「重ね重ね」「たびたび」や、生死を直接的に表現する「死ぬ」「生きる」などの言葉は使いません。「ご逝去」「ご生前」などに言い換えます。
- 時候の挨拶は不要:「拝啓」などの頭語や、季節に関する時候の挨拶は省略します。すぐにお悔やみの言葉から書き始めましょう。
- 薄墨で書く:筆ペンや万年筆を使う場合は、薄墨のものを選びます。「悲しみの涙で墨が薄まった」という意味を表します。ボールペンで書く場合は、黒色で構いません。
- 句読点は使わない:句読点は文章を区切る、終えるという意味があるため、古くから弔事の手紙では使わないのが慣習です。句読点の代わりにスペース(空白)を使います。
関係性別のメッセージ文例
相手との関係性に合わせて、言葉を選ぶことが大切です。
▼友人・知人へ
〇〇様(故人名)の御逝去の報に接し ただただ驚いております
ご家族の皆様のお悲しみはいかばかりかとお察し申し上げます
心ばかりの品をお送りいたしましたので 御霊前にお供えいただければと存じます
どうかご無理なさらないでください
心よりご冥福をお祈りいたします
▼会社関係者へ
〇〇(故人の役職・氏名)様の突然の悲報に接し 社員一同 謹んでお悔やみ申し上げます
ご生前の数々のご功績に深く敬意を表しますとともに 安らかなるご冥福を心よりお祈り申し上げます
心ばかりではございますが お花をお送りいたしましたので 御霊前にお供えください
▼後から訃報を知った場合
このたびは〇〇様(故人名)の御逝去を知り 大変驚いております
存じ上げなかったとはいえ お悔やみも申し上げず失礼いたしましたことをお許しください
遅ればせながら 心ばかりの品をお贈りいたしました
御仏前にお供えいただければ幸いです
ご家族の皆様におかれましては どうかご自愛くださいませ
大切なのは、定型文をなぞるだけでなく、自分の言葉で故人を偲び、遺族を気遣う一文を加えることです。
「〇〇様にはいつも笑顔で接していただき感謝しております」「ご家族の皆様の健康を心よりお祈りしております」といった言葉が、ご遺族の心を温めるでしょう。
まとめ:お悔やみに線香以外の品物で大切なこと
ここまで、お悔やみに線香以外の贈りものを選ぶ際の様々なマナーや具体的な品物について解説してきました。
たくさんの情報がありましたが、最も根底にあるべき大切なことは、終始一貫しています。
それは、「故人を心から悼み、悲しみの中にいるご遺族の気持ちに寄り添う」という真心です。
お悔やみに線香以外の品物を選ぶという行為そのものが、相手の宗教や生活環境、健康状態などを思いやる、深い配慮の表れと言えます。
どの品物を選ぶか迷ったときは、この原点に立ち返ってみてください。
ご遺族の負担にならず、少しでも心が和らぐものは何か。
故人が見たら、きっと喜んでくれるものは何か。
そう考えて選んだものであれば、たとえそれが高価なものでなくても、あなたの温かい弔意は必ず伝わるはずです。
そして、数ある選択肢の中でも、もしあなたが「どのような相手にも失礼なく、格調高い形で気持ちを伝えたい」と考えるのであれば、胡蝶蘭は非常に優れた贈り物となります。
その上品な佇まい、故人への敬愛を示す花言葉、そしてご遺族への負担が少ないという実用性。
これら全てが、お悔やみの場に求められる要素を満たしています。
品物選びは、故人との最後の対話であり、ご遺族への静かなエールです。
この記事で得た知識を参考に、あなたが自信を持って、心からの気持ちを伝えられることを願っています。
- ➤お悔やみに線香以外の贈り物は失礼にあたらない
- ➤宗教や住宅事情への配慮から線香以外が喜ばれることもある
- ➤贈り物を選ぶ際は掛け紙や包装などの基本マナーを守る
- ➤金額相場は3,000円から10,000円が一般的で関係性で調整する
- ➤宗教ごとにマナーは異なりキリスト教や神道では線香を使わない
- ➤肉や魚などの生臭ものやお祝いを連想させる品はNG
- ➤贈るタイミングは葬儀後から四十九日までの間が一般的
- ➤品物は日持ちする個包装のお菓子などが喜ばれる
- ➤飲み物はご遺族が消費しやすいお茶やコーヒーのセットが良い
- ➤優しい光の絵ろうそくも心のこもった贈り物になる
- ➤お花を贈るなら格式高く万能な胡蝶蘭が最適
- ➤胡蝶蘭は香りや花粉が少なく手入れも簡単で負担をかけない
- ➤品物には必ず簡潔なお悔やみメッセージを添える
- ➤メッセージでは忌み言葉や句読点を避けるのがマナー
- ➤最も大切なのは故人を偲び遺族を気遣う気持ち










